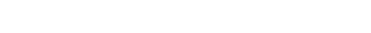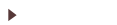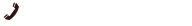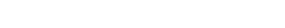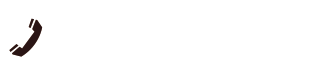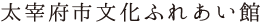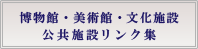学芸だより
幸橋と關内記の奮闘
太宰府市朱雀の榎社と、北側にある幼稚園との間に流れる水路の辺りは「幸橋」と呼ばれており、かつてはこの場所に小さな橋が架かっていたといわれています。
この幸橋は、近世に記された『九州記』や『高橋記』等の戦国期の九州を題材とした軍記物の中で、肥前の筑紫氏が四王寺山に築かれた岩屋城を攻めた際の戦いの舞台の一つとして登場します。天正7年(1579)、岩屋城を守る高橋紹運の家臣である關内記が、銃撃を受けて退却する筑紫勢に対し追撃を行いました。ところが反撃に転じられたため、内記は幸橋において、敵に斬られて深手を負いながらも長刀を振るい奮闘した、という内容が記されています。
現在、幸橋は道路の境界ブロックに地名が刻まれるのみですが、天正期の太宰府の物語を伝える貴重な場所の一つです。
学芸員 松村 和